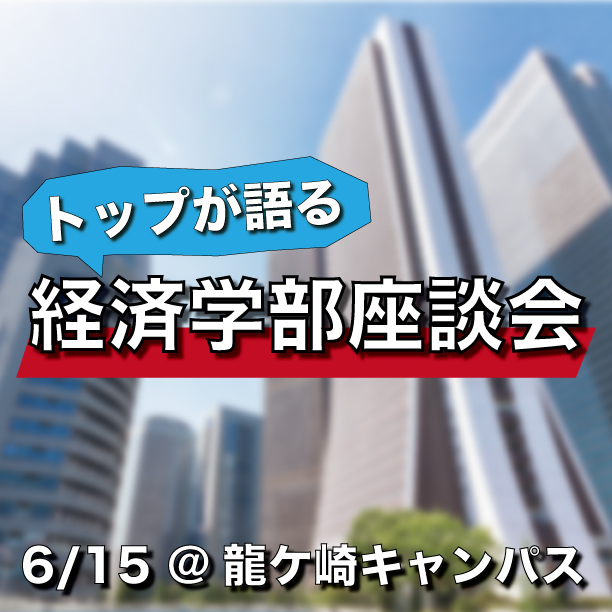経営全般の理論修得と実践を通じて
現場の多様な課題に応えていく
経済学部
龍ケ崎 新松戸

経済学部
経営学科
学びの特色
-
特色1

多彩な体験学習で
起業家精神を養成現役社長による「起業家育成講座」や流経大出身の税理士による授業、企業研究ゲームなど、実社会に即した体験学習で実践力を養います。
-
特色2
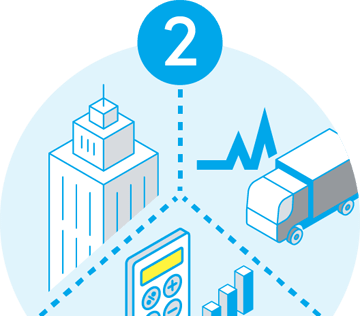
自分の興味から選べる
3つのフィールド2年生からは「起業・マネジメント」「流通・マーケティング」「会計・ファイナンス」の3つのフィールドから進路に合わせて科目を選択できます。
-
特色3

ICT時代に即した
最新の経営学を学修ネット社会における消費者ニーズの捉え方などPCを活用したICT時代の経営学を学び、これからの企業経営を牽引する人材を育てます。
学びの分野
-
流通・マーケティング
#マーケティング #流通 #消費者行動 #商品開発 #広告 #ブランド
変化する消費市場に受容される製品・コンセプト・ブランドを形成する方法や、多様化するライフスタイルに対応する生産者と販売業者の関係を構築する方法を学んでいきます。 -
起業・マネジメント
#経営戦略 #経営組織 #リーダーシップ #イノベーション #ベンチャービジネス
消費者ニーズの多様化に伴う環境変化に対応して意思決定を行うとともに、組織を動かし、事業を創造・展開していくための知識と技術を身につけます。 -
会計・ファイナンス
#財務会計 #原価計算 #管理会計 #財務管理 #監査
企業に関する資金の流れを数字の面から理解するとともに、自社の経営の良し悪しを判断するための方法や、企業が資金を調達するための手法を修得します。
経営学科の“実学”
-

株式を売買し、
変動の理由を学ぶ「企業研究ゲーム」2年生全員が企業研究ゲームに挑戦し、東証グロース市場で実際に取引されている株式を売買します。なぜ株価が変動したのかを深く考え、企業活動やその成長メカニズムを学びます。
-

起業とビジネスによる
社会的課題の解決(中溝ゼミ)「自らビジネスを創めること」が主なテーマです。ゼミではテキストを読み、ディスカッションし、さらに企業の経営者の方から話をうかがったりして、社会的な課題や起業、最新のビジネスについて学んでいきます。
経営学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)
- マネジメントの基礎知識を高レベルで身につける(梅木ゼミ)
- 消費者行動研究とマーケティング実践/コミュニケーション力の向上(小沢ゼミ)
- マーケティングと消費者行動の基礎を学ぶ (加藤ゼミ)
- 流通現象を自ら分析できるようにする(呉ゼミ)
- ビジネスプランを実践的に学ぼう(崔ゼミ)
- 経営情報の活用とアントレプレナーシップを学ぼう(難波ゼミ) など
カリキュラム
1年生
| 必修科目 基本科目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 必修科目 専門共通科目 |
|
||
| 選択必修科目 専門基礎科目 |
|
||
| 選択必修科目 専門発展科目 |
|
||
2年生
| 学びの分野 |
起業・マネジメント
|
流通・マーケティング
|
会計・ファイナンス
|
|---|---|---|---|
| 必修科目 基本科目 |
|
||
| 選択必修科目 専門共通科目 |
|
||
| 選択必修科目 専門基礎科目 |
|
|
|
| 選択必修科目 専門発展科目 |
|
|
|
3年生
| 学びの分野 |
起業・マネジメント
|
流通・マーケティング
|
会計・ファイナンス
|
|---|---|---|---|
| 必修科目 基本科目 |
|
||
| 選択必修科目 専門基礎科目 |
|
|
|
| 選択必修科目 専門発展科目 |
|
|
|
4年生
| 学びの分野 |
起業・マネジメント
|
流通・マーケティング
|
会計・ファイナンス
|
|---|---|---|---|
| 必修科目 基本科目 |
|
||
授業Pick up
事業創造論Ⅰ
さまざまなアクティブ・ラーニング手法や企画案発表会などを通じて、事業創造に関する基礎知識や起業する上で欠かせない新規事業の企画力に加え、ビジネスモデルを構築できる能力を実践的に身につけることを目指しています。


- 第1回 現代における「起業」とは 社会的起業Ⅰ
- 第2回 会社の作り方
- 第3回 現代ビジネスにおけるマーケティング・ICTの活用
- 第4回 起業家支援
- 第5回 リピーターと定期収入
- 第6回 ビジネスプランの作り方
- 第7回 「人に働いてもらう」ということ
- 第8回 ゲストスピーカーによる講演
- 第9回 事業継承とM&A
- 第10回 地域の新興企業研究
- 第11回 ビジネスコンテスト 動画の視聴
- 第12/13回 ローカルビジネス
- 第14/15回 ビジネスコンテスト プレゼンテーション
経営入門
経営学を初めて学ぶ人を対象に、身近な企業の事例をもとにケーススタディとグループワークの実践を通じて、経営に関わる現象に触れるとともに、企業経営の基本的な仕組みについて学びます。
ビジネスプランコンテスト
(株)マイナビが運営する「キャリアインカレ」などのビジネスプランコンテストへの出場を通じて、実際の企業や社会、地域が抱えている問題や課題に対する解決策を導き出す力と、自らの考えや意見を相手にわかりやすく伝える発信力を養います。
STUDENT’S VOICE

美容分野で起業するのが
私の夢
美容の分野で将来起業するのが私の夢です。夢を実現するために、マーケティングに関する知識や、リーダーシップ、コミュニケーションスキルなど、経営者に必要な能力を身につけるよう努力してきました。この経験を活かして、今後企業経営に携わりたいと考えています。
経済学部 経営学科 2年(取材当時)
山﨑 綾香さん
山﨑さんの1日のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 : 00–10 : 30 | |||||
| 2 | 10 : 45–12 : 15 | 2年演習 (ゼミ) |
マーケティング論Ⅱ | English Communication 初級Ⅱ |
流通論Ⅱ | |
| 3 | 13 : 05–14 : 35 | リベラル アーツ演習 |
アジア文化論Ⅱ | 経営財務論Ⅱ | ||
| 4 | 14 : 50–16 : 20 | 広告論Ⅱ | ブランド論Ⅱ | |||
| 5 | 16 : 35–18 : 05 | 金融論Ⅱ | ||||
| 6 | 18 : 20–19 : 50 | 消費者行動論Ⅱ | ||||
株式会社千葉銀行 内定
実践的な学びがアピールできた
就職キャリア支援センターでは企業探しから面接対策まで、幅広くサポートをしていただきました。学内でのお弁当コンペや学科主催のプレゼン大会など、実践的な学びが他大学にはない強みとしてアピールできたことも大きかったと思います。将来的には、ゼミで学んだマーケティングの知識が活かせる部門に携わりたいですね。
経済学部 経営学科 渋谷 智菜さん

GRADUATES’ VOICE

2021年3月 経済学部 経営学科 卒業
池田 敦哉さん
私の出身地・茨城県の経済発展に貢献したいという想いで就職活動を行い、さまざまな企業と関わりのある常陽銀行に就職しました。現在担当している法人営業は、銀行のサービスを提案するだけでなく、人材の紹介や企業のマッチングなどを行い、取引先の企業が長く継続するためにサポートする仕事です。その過程で、各企業の財務状況などのデータを見て課題を把握していくのですが、大学で指標分析や簿記、財務会計について学んだことで、書かれている数字の意味を理解しながら、データ分析が進められていると感じています。今後もこの力を活かして、取引先の課題解決に励んでいきます。
取得可能な教員資格
- 高等学校教諭一種免許状「商業」
目指せる進路
- 経営者
- コンサルタント
- 企画業務・経営幹部
- 銀行員・証券アナリスト
- 公認会計士
- 税理士
- マーケティング・商品企画部門 など








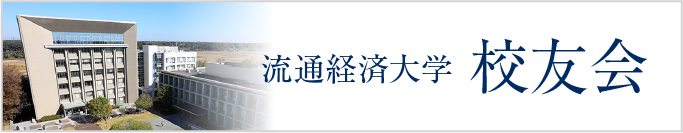





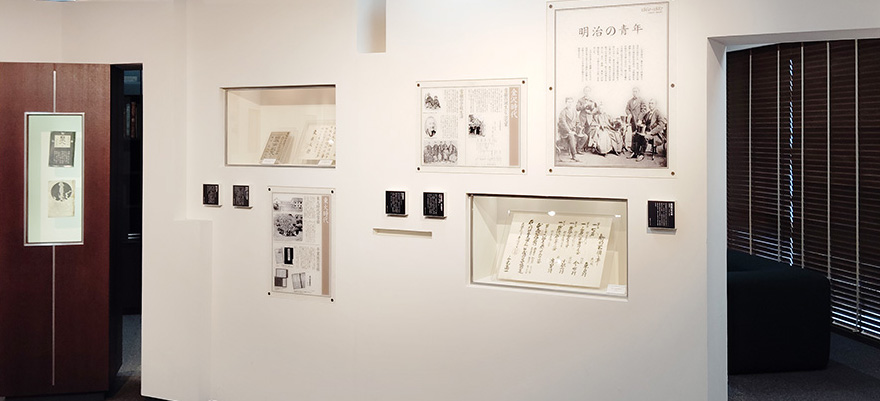











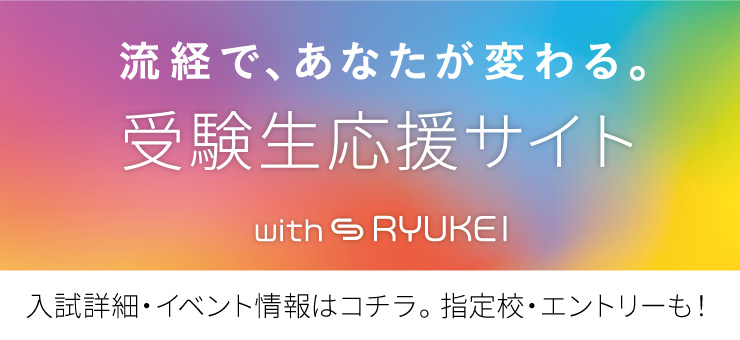
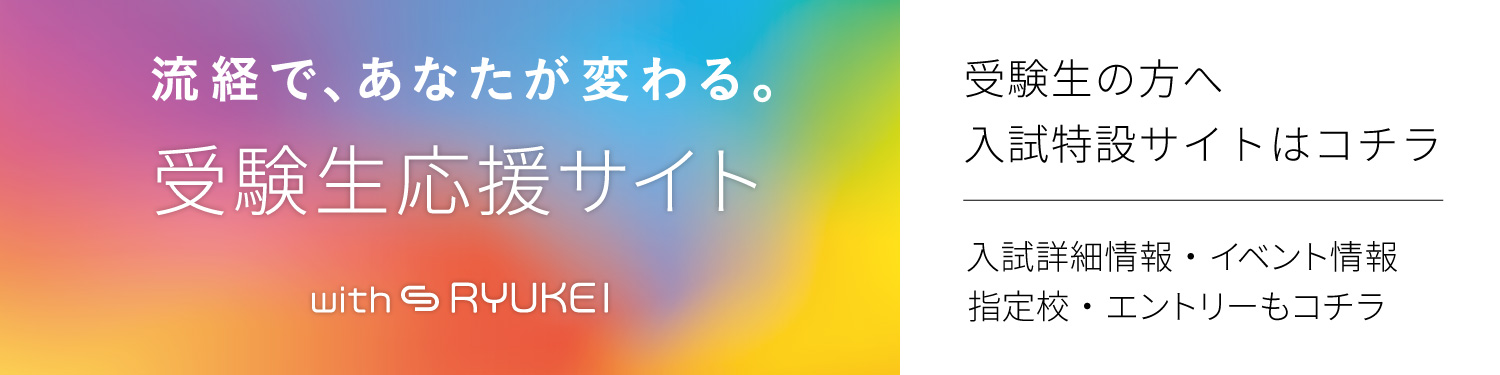
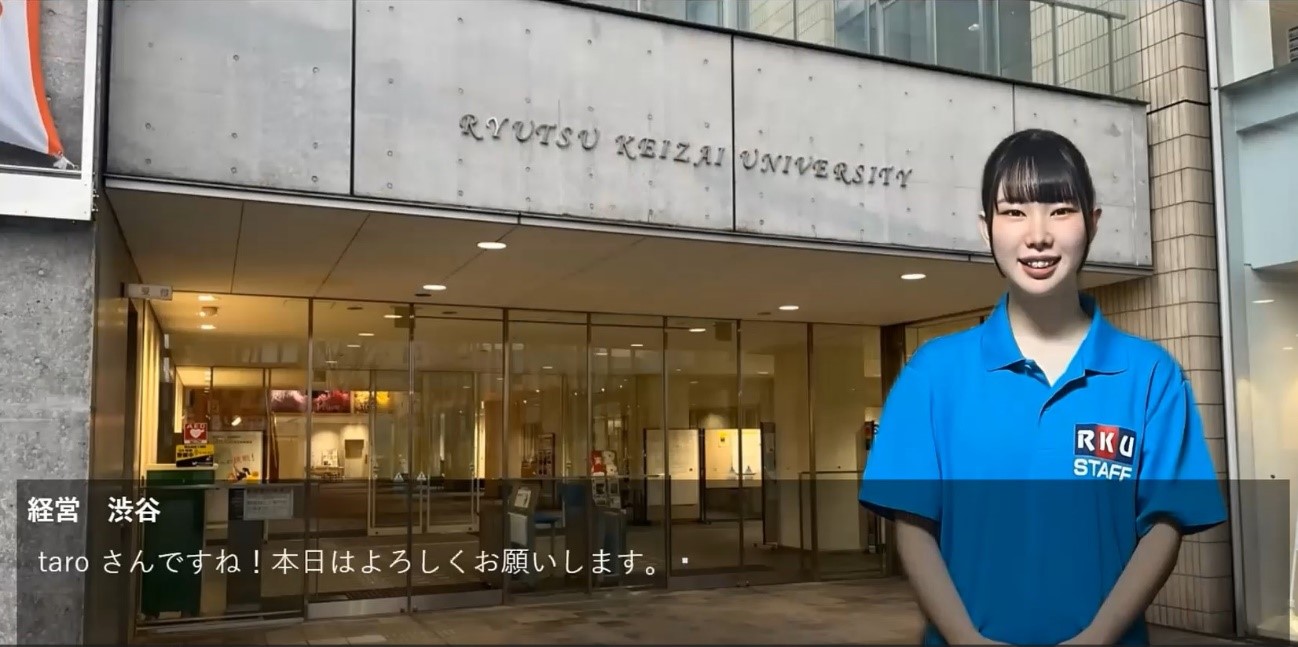
 写真:流通経済大学PRノベルゲームの1シーン
写真:流通経済大学PRノベルゲームの1シーン