競技スポーツから生涯スポーツまで、
子どもから高齢者まで、
幅広くスポーツの指導や
社会貢献に関わる人材を養成します
スポーツの競技力向上、青少年から高齢者にいたる
健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進に
寄与できる人材を養成します。
龍ケ崎

スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学科
競技スポーツから生涯スポーツまで、
子どもから高齢者まで、
幅広くスポーツの指導や
社会貢献に関わる人材を養成します
スポーツの競技力向上、青少年から高齢者にいたる
健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進に
寄与できる人材を養成します。
龍ケ崎
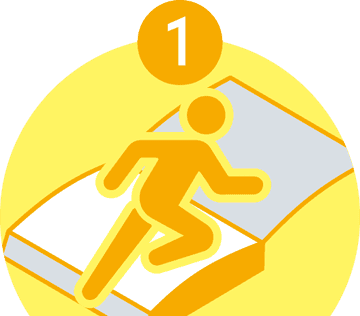
将来スポーツに関する仕事に就きたいあなたへ、教員やトレーナー以外にもスポーツに関する仕事はたくさんあります。あなたが楽しいと思える・あなたに合うスポーツに関する知識やスキルが学べます。

学科に所属する全員が救急救命の資格取得を目指します。今後、スポーツに関わる際には、「安全」はどのような分野でも必要な知識とスキルになります。

「健康づくりのプログラムを考案し、地域や病院で実践する」「地域や学校で子どもたちにスポーツの指導をする」など、実践的な機会が豊富です。

スポーツ健康科学科は学外での学びの場が多く、貴重な経験をたくさん積むことができています。ゼミの一環で、小学校を訪ねて体育の授業の補佐をしたり、コミュニティセンターで高齢者向けのスローエアロビクス教室を開催したりしました。地域の方々と触れ合いながら学んだ知識やスキルは、私が目標にしている体育教員になってからも活きる力になりそうです。
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 3年
沼田 凌汰さん
| MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 9:00〜10:30 |
生命科学Ⅱ | 教育社会学概論 | |||
| 2限 10:45〜12:15 |
生態学Ⅱ | 生徒指導論 | 特別活動及び 総合的な学習の 時間の指導法 |
||
| 3限 13:05〜14:35 |
スポーツ政策論 | バスケットボール | キャリア デザインⅡ |
3年演習 | |
| 4限 14:50〜16:20 |
教育実習 (事前指導) |
アダプテッド・ スポーツ論 |
スポーツ史 | ||
| 5限 16:35〜18:05 |
道德教育論 | スポーツリーダー 実習 |
| 学びの分野 |
スポーツ教育
|
競技スポーツ
|
生涯スポーツ
|
スポーツトレーナー
|
スポーツ教養
|
|---|---|---|---|---|---|
| 必修科目 基本科目 |
|
||||
| 必修科目 学部学科科目 |
|
||||
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅰ |
|
||||
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅱ |
|
||||
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅲ |
|
||||
| スポーツ実技科目Ⅰ |
|
||||
| スポーツ実技科目Ⅱ |
|
||||
| スポーツ実技科目Ⅲ |
|
||||
| スポーツ実技科目Ⅳ |
|
||||
| 選択科目 専門発展科目 |
|
|
|
||
| 選択科目 外国語科目 |
|
|
|
|
|
| 自由科目 資格科目 |
|
||||
| 学びの分野 |
スポーツ教育
|
競技スポーツ
|
生涯スポーツ
|
スポーツトレーナー
|
スポーツ教養
|
|---|---|---|---|---|---|
| 必修科目 基本科目 |
|
||||
| 必修科目 学部学科科目 |
|
||||
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅰ |
|
|
|
|
|
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅱ |
|
|
|
|
|
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅲ |
|
|
|
||
| 選択科目 専門発展科目 |
|
|
|
|
|
| 自由科目 資格科目 |
|
|
|
||
| 学びの分野 |
スポーツ教育
|
競技スポーツ
|
生涯スポーツ
|
スポーツトレーナー
|
スポーツ教養
|
|---|---|---|---|---|---|
| 必修科目 基本科目 |
|
||||
| 必修科目 学部学科科目 |
|
||||
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅰ |
|
||||
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅱ |
|
||||
| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅲ |
|
||||
| 選択科目 専門発展科目 |
|
|
|
|
|
| 自由科目 資格科目 |
|
|
|||
| 学びの分野 |
スポーツ教育
|
競技スポーツ
|
生涯スポーツ
|
スポーツトレーナー
|
スポーツ教養
|
|---|---|---|---|---|---|
| 必修科目 基本科目 |
|
||||
| 自由科目 資格科目 |
|
|
|||
大学で得た経験が
選手のサポートの土台になっている
2023年3月 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科卒業
松本 莉生さん
現在は、サッカークラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉レディース」にフィジカルコーチとして所属し、女子中高生の選手を対象に、ケガ予防のためのトレーニングやリハビリ明けのサポートを行っています。大学で入ったライフセービングクラブ・コンディショニングチームで女子サッカー部をサポートしていた時に、ケガで長期離脱する選手を減らしたいと感じ、フィジカルコーチを志しました。在学中に機能解剖学や測定理論実習、スポーツ栄養などの授業で知識を身につけていたため、現在のチームのメディカルスタッフともコミュニケーションが取りやすく、スムーズなサポートにつながっています。

スポーツ健康科学科では 、「スポーツの競技力向上、青少年から高齢者にいたる健康の維持・増進活動、学校教育や社会教育の推進に寄与できる人材の養成」を目指しており、所定の単位を修得し、以下のような知識や技能、態度を身に付けた 学生の卒業を認定し、学士(スポーツ健康科学)の学位を授与します。
DP1
人文・思想、地域・歴史、社会、自然および健康、キャリア、外国語などのゆたかな教養と見識を身に付けている。
DP2
生命教育を中心としたスポーツ健康科学の学問内容および方法を理解している。
DP3
自ら設定した課題について、スポーツ健康科学の学問領域の知識を用いて考察することができる。
DP4-1
自分の考えを口頭表現、文章表現や身体表現によって的確に伝えることができる。
DP4-2
スポーツ健康科学の知を実践の力へと高め、地域社会および国際社会のニーズにこたえることができる。
スポーツ健康科学科では 、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げた能力を修得させるために、以下のような教育内容および教育方法に基づき教育課程表(カリキュラム)を体系的に編成・実施するとともに、教育評価を行います。
CP1
国際化社会において必須となる外国語によるコミュニケーション力を育成する科目を配置する。(DP1)(DP1-1)
CP2
人文科学、社会科学、自然科学に対する理解を深める教養科目を配置する。(DP1)
CP3
生涯学習のための基礎的知識と自己実現に向けた能動的な姿勢を育成するキャリア科目を配置する。(DP1)
CP4
教員免許のほかスポーツ健康にかかわる資格を取 得するための資格科目を配置する。(DP1、DP2、DP3、DP4-1、DP4-2)
CP5
「生命(いのち)の尊厳」と「人間力」を持った人材の育成を特に重視して必修科目を配置する。(DP2、DP3、DP4-1)
CP6
コミュニケーション力および課題発見・解決能力を育成するため 、演習科目を配置する。(DP3、DP4-1、DP4-2)
CP7
今日、スポーツ科学を構成している学問を幅広く修得させる専門基礎科目を配置する。(DP2、DP3)
CP8
発展的かつより専門性を持ったカリキュラムを構成するために専門発展科目を配置する。(DP2、DP3、DP4-1、DP4-2)
CP9
スポ―ツの競技力向上を図る科目を配置する。(DP2)
【教育方法】
【教育評価】



