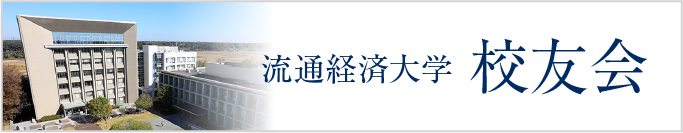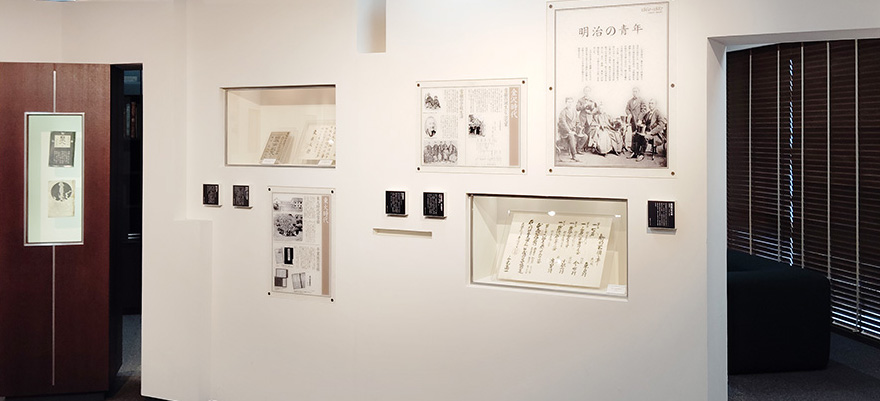共創社会学部
社会学科 下司ゼミ
- 教 員
- 下司 優里(ゲシ ユリ)准教授
- 専門分野
- 障害者福祉、障害児教育
- 所属期間
- 2年次 通年
- 構 成
- 14名(うち留学生2名)
- キャンパス
- 新松戸キャンパス
※取材時(2025年1月14日)の情報に基づく

障害と社会を考える
体験から深める福祉の視点

下司 優里 准教授
2年 寺本さん
下司ゼミってこんなゼミ
「障害者福祉」を専門とし、社会と障害の関係について、体験型の学びを通して多角的に考察します。2年次は社会学・心理学・保育など幅広い視点から基礎を築き、グループワークやジェスチャーゲーム、視覚障害の疑似体験などを通して共感力を育みます。3年次以降はレポートや発表、児童発達支援施設の見学を通じて専門性を深め、自身の関心や進路の方向性を探ります。福祉や保育を目指す学生はもちろん、将来の進路が明確でない学生にも開かれたゼミです。他者を尊重し、自分の価値を見つめ直す福祉マインドを育む場となっています。
下司ゼミでは、どのような活動をしますか?
下司先生:「障害者福祉」を中心テーマとして、社会と障害の関係を広い視点から考えていきます。2年生の初めは、ゲームやアクティビティを取り入れながら、障害について触れていきます。たとえば、言葉を使わずにジェスチャーで伝える「ジェスチャーゲーム」や、視覚障害を疑似体験する「ブラインドウォーク」などを通じて、障害のある方の視点を体感的に理解します。
寺本:ブラインドウォークでは「視覚障害者の立場になる」という視点にハッとさせられました。障害のある方や子どもなど、立場の異なる人の気持ちを想像し、考えることがとても大切だと実感しました。他にも、松戸市内の児童発達支援センターへ訪問するなど、フィールドワークの機会が多くあります。

下司先生:本学科には保育士や教職を目指す学生が多くいますが、地域の保育園に通える子どもばかりではありません。障がいや医療的ケアの必要な子どもたちもいて、そうした子どもたちの保育という選択肢もあるのです。そういった実情や多様な現場を知ることで、将来の進路をより深く考えるきっかけになるといいと思っています。
ゼミの活動を通じて、成長を感じたことはありますか?
寺本:現在、障害児デイサービスで、放課後や長期休暇中に、障害のある子どもたちを見守るアルバイトをしているんですが、ゼミでの学びを通して、子どもとの接し方や関係の築き方が深まってきたことを感じています。子どもたちと関わる中で実感するのは、「テンション」や「ノリ」の大切さ。こちらが明るく楽しそうに関わると、子どもたちも自然と笑顔を見せてくれたり、心を開いてくれるんです。何気ないやりとりの中に、関係性を深める瞬間があるんだなと。ゼミでの学びが、現場での一つひとつの行動に確かに生きていると実感しています。
下司ゼミの魅力はどんなところですか?

寺本:下司先生は配布資料がわかりやすく、動画など教材も充実していて、福祉の現場のリアルな様子を学べるのが魅力です。また、発表の機会も多く、プレゼン力の向上にもつながっています。
下司先生:発表の機会を多く設けているのは、ゼミの雰囲気づくりという面もありますが、何より「自分の興味関心に気づいてほしい」という思いがあるからです。人の話を聞いて共感したり、逆に「自分はそこにはあまり関心がないな」と気づくこともありますよね。「話すこと」と「聴くこと」、その両方を通して、自分自身の興味や視点を深めていってほしい。そしてそれは、福祉の現場で人と向き合ううえでも、とても大切な力につながっていくはずです。
将来はどんな職業を目指していますか?
寺本:僕は高校2年生の頃からボランティアに参加するようになり、地域のイベントや子ども向けの料理教室で子どもや困っている方と関わる中で、「人を支える仕事って素敵だな」と思い、福祉の道に興味を持つようになりました。下司ゼミに入って、さまざまな障害者福祉について学んでからは、その目標がより具体的になり、現在は、障害のある子どもや、不登校の子のサポートに関わる福祉の仕事を考えています。
下司先生:私の持つ知識や経験が、障害のある子どもたちの支援に役立つよう、これからも惜しみなく伝えたいていきます。でも、下司ゼミに入るからといって全員が福祉の道に進む必要はありません。むしろ「福祉マインド」、つまり他者を尊重し、自分も大切にする気持ちは、どの道に進んでも活かされると信じています。だからこそ、進路が定まっていない学生も、違う専門を目指す学生も、安心して来てもらいたいと思います。