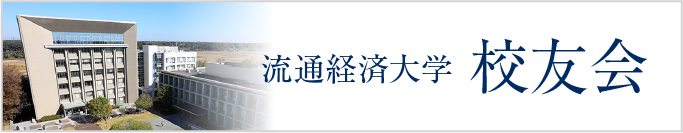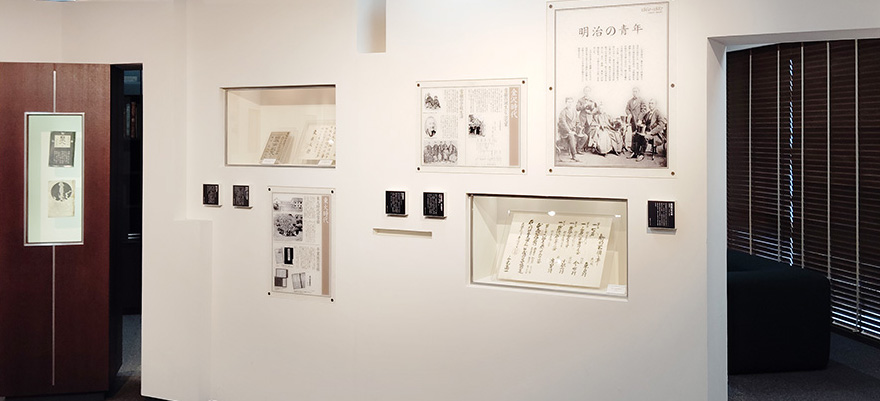流通情報学部
流通情報学科 天野ゼミ
- 教 員
- 天野 俊一(アマノ シュンイチ)准教授
- 専門分野
- 複雑系科学
- 所属期間
- 3〜4年次 通年
- 構 成
- 12名(うち留学生6名)
- キャンパス
- 新松戸キャンパス
※取材時(2025年1月14日)の情報に基づく

データで読み解く社会のしくみ
複雑系科学で考える人と組織

天野 俊一 准教授
4年 関口さん
天野ゼミってこんなゼミ
天野ゼミでは、情報科学の中でも「複雑系科学」を基盤に、統計理論とプログラミングを用いて、さまざまなデータを分析していきます。3年次ではプログラミング言語(R言語など)を活用しながら、ビッグデータの解析や多変量解析など応用的な内容に挑戦します。データ分析を通じて社会の仕組みを捉え、実社会に役立つ分析力や思考力を育成します。4年次で行う卒業研究では、学生自身の関心に基づいた仮説立案・実験・分析を重視し、自ら問いを立て、検証する力を養います。希望者は企業との共同研究に参加できるチャンスも。情報・統計分野に限らず、柔軟な思考と対話力を鍛えたい人におすすめのゼミです。
天野先生のご専門「複雑系科学」とは、どのような学問なのでしょうか?
天野先生:情報科学の一分野ですが、その中でも、いろんな人や社会の動き、生物現象など、複雑な現象をデータや数式を使って理解しようとする学問です。最近では、企業や組織の活動から得られるビッグデータを使って、「今この集団はどんな状態なのか」「どんな特徴があるのか」といったことを数値で表したり、可視化したりする研究をしています。それをもとに、企業の組織改善や働き方改革など、組織運営に役立てるような取り組みにもつなげています。今、とても注目されている分野ですよ。

関口:一見、すごく難しそうに感じますが、勉強すればするほど、「もっと知りたい」と思える分野ですよ。私は2年生から天野ゼミで、統計やR言語というプログラミングに触れる機会があって、すごく面白いと感じたんです。データをグラフにしたり、見える形にできるのが楽しくて。もっと深く学びたいと思い、3年生でもこのゼミを選びました。ゼミでは、ニュースで取り上げられるような時事問題や、スポーツ、芸能といった身近なテーマも扱いながら、データ解析を学びます。身近な話題が分析の対象になることで、学びがグッと現実に近づいてくる感じがするんです。そのおかげで、自然と社会に目を向ける視点も育ってきたように思います。
――ゼミでは、どのよう流れで学びを進めていきますか?
天野先生:3年生では、まず統計の基本を学ぶところから始めます。計算の意味や仕組みを理解することを大切にしているので、紙と鉛筆での手計算が中心。後半はグループでテーマを決めて、AIの基礎に触れることもあります。またR言語を使った実習に加えて、複雑なデータの分析やグループ研究など、卒論につながるような力もつけていきます。
関口:R言語とは、CSVファイルのようなデータを読み込んで統計解析をしたり、グラフなどの視覚的な表現を行うためのプログラミング言語です。使いやすくて、統計の計算やデータの見える化にとても向いているので幅広く活用されている言語です。3年生のゼミでは、このR言語を本格的に使って、ビッグデータの解析や多変量解析にもチャレンジしていきます。
ゼミ活動で印象に残っていることは?
関口:グループワークが印象に残っています。統計の問題をグループで手計算したり、テーマを決めて作品を作ったり、みんなで協力して進めることが多かったです。特に、コロナ禍では友だちと会う機会が少なかったので、ゼミでの交流は貴重でした。ゼミの活動を通して仲間とのつながりができ、自分から積極的にコミュニケーションを取る力も養われたと感じています。
天野先生:関口さんは、最初はおとなしい印象でしたが、だんだんとリーダーシップを発揮して、ゼミ長としても活躍してくれました。グループワークなどでもリーダー役を務めることが多く、データの分析や発表など、いろいろな場面で力を発揮してくれました。
希望者は学外での活動にも参加できるそうですね。
天野先生:はい。希望する学生には私が担当している企業との共同研究に参加してもらうこともあります。たとえば、物流会社の倉庫で人の動きをセンサーで記録して、それを分析して、より働きやすくするための仕組みを考えたり、実際にシステムを開発したり。学生も一緒に実験をしたりデータを解析したりして、現場でのリアルな経験ができるんです。関口さんも、積極的に参加してくれましたね。
関口:企業との共同研究に参加できるチャンスは貴重だと思い、参加しました。企業の人たちが行う研究を間近で見ることができ、また現場での気づきや課題を直に感じられて、教室では得られない経験ができたと感じています。私の卒業研究のヒントももらえました。
卒業論文ではどのようなテーマに取り組んだのですか?

関口:物流の倉庫で行われるような単純作業において、「音のテンポが変わると作業にどんな影響が出るのか」を調べました。テンポがだんだん速くなるパターン、遅くなるパターン、ずっと同じテンポのパターンの3つで実験をして、作業量や時間の感じ方にどう違いが出るのかを比べました。その結果、テンポが遅くなるパターンの方が、作業が安定する傾向が見られました。R言語を使ってデータを分析し、統計的にも検証しました。
天野先生:関口さんの卒論は、企業との共同研究で得た経験をベースに、自分で仮説を立てて実験して結果をまとめた、非常に完成度の高いものでした。実験の設計やデータの取り方も工夫されていて、よく頑張ってくれたね。
就職はどのような分野に進みますか?
関口:高校は情報科出身で、大学でも情報技術に触れてきたので、将来も情報系の仕事に就きたいと思っていました。大学では実際にプログラムを書いたり、データを扱ったりする経験ができたことで、よりその意志が強まりました。就職は自分の希望通り、情報系の企業に決まりました。システム開発や運用など、情報技術を活かして社会に貢献できる仕事を目指しています。
天野先生:社会に出ると、技術だけでなく、人とどう関わるかも大事になってきます。関口さんはゼミを通じて、その両方をバランスよく身につけてきたので、きっとどこに行っても活躍してくれると期待しています。