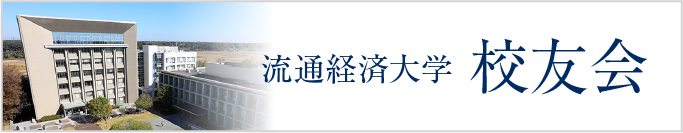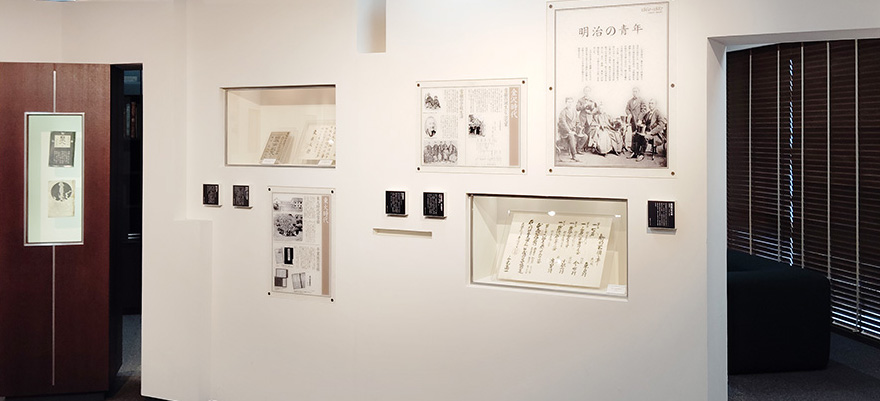身近な生活と法律のつながりを学ぶ!〜民法総則の授業の魅力とは〜 法学部で広がる未来の自分の可能性:第34回
法律は、私たちの日常生活と密接に関わっています。スマホの契約や友人とのお金の貸し借りも、実は「民法」という法律のルールに基づいて行われています。今回は本学法学部で「民法総則」の授業を担当する大塚先生に、生活に身近な例を交えながら、授業のなかで何を学べるのかを伺いました。自分や周囲の人を守る力を身につけることのできる、とても魅力的な授業となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。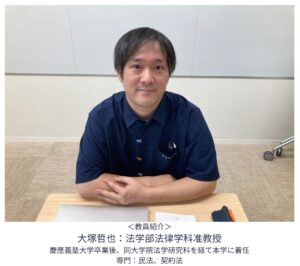
──本日はよろしくお願いいたします。まずはじめに、大塚先生が民法を研究しようと思ったきっかけを教えてもらえますか?
大塚:民法を研究しようと思ったきっかけはいろいろあるのですが、一番の理由は、民法が私たちの生活に最も身近な法律だと感じたからです。例えば、友達にお金を貸したり、スマホを分割払いで買ったり、アパートを借りたり。こうした日常の何気ない行動一つひとつについての「ルール」を整理してくれているのが民法なんです。そう考えたらとても面白くて、民法を研究したいと考えるようになりました。
──ありがとうございます。では、先生が担当されている「民法総則」という授業ではどんなことを学ぶんですか?
大塚:民法にはたくさんのルールが定められているのですが、その「入口」にあたる部分が「総則」です。ここでは「社会生活の大原則」とでもいうべきルールが書かれています。例えば「18歳から大人として扱われる」といった年齢に関する決まりや、「契約はどうすれば成立するのか」といった契約の基本ルールが定められています。このような社会生活の基本ルールを学ぶのが「民法総則」の授業です。
──大学生や高校生の日常生活とも関係があるのでしょうか?
大塚:大いにあります。例えばアルバイトをするときの「雇用契約」、スマホやパソコンを買うときの「売買契約」、定期券の購入契約などは、すべて民法総則に定められたルールを基礎にして行われています。また、2022年から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、これも民法総則に定められたルールです。18歳になれば保護者の同意なしに自分で契約ができる一方で、トラブルに巻き込まれるリスクも増えるという話は聞いたことがあると思います。このような社会問題の背景にあるルールを理解するのが、まさに民法総則の学びです。
──ありがとうございます。では次に、民法総則を学ぶ意義や魅力はどんなところにあるのかも教えてください。
大塚:大きな魅力は「自分や他人を守れるようになる」ということです。法律を知っていると、どんな行為が正しくて、どんな行為が不公平なのかを冷静に判断できます。例えば、友達が怪しい契約を結びそうになったときに「それは危ないかも」と気づいて止められるかもしれませんし、自分自身が不利な条件を押しつけられたときに「これはおかしい」と堂々と言えるようになります。ルールを知ることで、安心して生きる力を手に入れることができるんです。
──将来の進路にはどうつながるのでしょうか?
大塚:もちろん弁護士や裁判官といった法曹を目指す人にとっては必須ですが、それ以外の道にも役立ちます。会社員として契約を結ぶ場面、公務員として市民の相談に応じる場面、さらには日常生活の中でも役に立ちます。社会に出れば誰もが契約やルールと関わらずにはいられません。だから民法総則の知識は「一生もの」だと言えるでしょう。
──最後に、読者の方へのメッセージをお願いします。
大塚:「法律」というと堅苦しいものに感じるかもしれませんが、実際には法律は皆さんの日常のすぐそばにあります。アルバイト、買い物、SNSでのやり取りも、法律の枠組みの中で行われています。大学で民法総則を学ぶことは、社会の仕組みを知り、自分の力で未来を切りひらく準備をすることでもあります。少しでも「面白そうだな」と思った人は、ぜひ法学部で一緒に学んでみましょう。
──大塚先生、本日はありがとうございました。