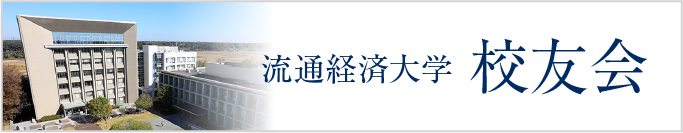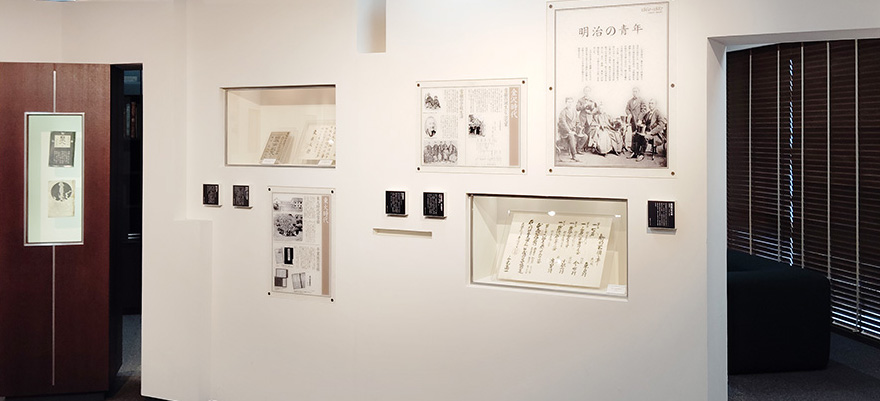法学部で広がる未来の自分の可能性 第33回 「田中ゼミで学ぶ、子ども子育て政策の自治体間比較」
法学部の田中ゼミには、地方自治の現場で働く自治体職員や、地域の暮らしに貢献する民間企業を目指す学生が集まっています。田中ゼミでは、政策の実情を肌感覚として理解する現場主義と、統計データを自ら分析して人前で発表するスキルの「二刀流」を到達目標としています。今回はゼミの特色や学生の成長を支える学びの魅力を、田中先生の言葉を通じてお届けします。ぜひ最後までご覧ください。
——本日はよろしくお願いいたします。それではまず、先生のご専門とゼミのテーマについて教えてください。
田中:私は現代日本政治・公共政策分析を専門としています。ゼミでは自治体の子ども子育て政策を題材に、松戸市と流山市の比較をしています。
——松戸市と流山市は隣り合う自治体ですが、子ども子育て政策に違いはあるのですか?
田中:さっそく良いご質問ですね。両市とも子ども子育て政策に力を入れていますが、すすめ方に違いがあります。例えば保育施設一つとっても、松戸市は施設の半数以上が3歳未満を対象とする小規模保育事業であるのに対し、流山市は約7割が公私立保育園です。
——実際にそれはどのような違いを生むのでしょう?
田中:小規模保育事業に通うお子さんは3歳になると別の施設を探さなければいけません。それは保護者にとって負担にはなりますが、既存の幼稚園施設を有効活用するという利点もあります。
——保育施設の違いについては考えたこともありませんでした。
田中:子育てに限らず様々な公共政策は、自分が当事者にならないと気がつかない問題が沢山あります。大学生は少子化問題の当事者になる人々ですから、現状を把握し自分の頭で考えてもらうようなゼミにしたいと思っています。
——現状を把握するためにゼミではどのような活動をおこなっていますか。
田中:ゼミではできるだけ現場に足を運ぶことを推奨しています。新松戸キャンパスのすぐ近くにある子育てひろば「ほっとるーむ新松戸」に今年もご協力いただき、学生が見学する機会をつくりました。子どもの純真さに「心が洗われた」と話す学生もいました。

——確かに大学生になると、きょうだいや親戚でもいない限り、小さなお子さんに接する機会は少なくなりますよね。
田中:そうなんです。子どもの動きを目にしたうえで、保護者や保育者がどのように子どもに接しているかを知ることは、政策を考えるうえでも、将来自分が家庭をもつ際の心の準備としても、大事なことだと思います。
——ゼミでは他にどのような活動がありますか。
田中:そうですね、他には地方議会の傍聴があります。今はインターネットで気軽に議会中継を見ることができますが、傍聴することで議場の雰囲気や野次の様子、傍聴者にどんな人がいるのか、といった数多くの情報が得られます。有権者が選んだ首長と議会議員はどのように仕事をしているのか、自分の目で確認することも重要です。さらにいえば、若い世代が傍聴にきていること自体、地方議会にも「見られている」という緊張感をもたらす効果があるのです。
——議会ではどのようなことが話し合われているのでしょうか。
田中:今回は「高齢者の看取り」に関する質疑を傍聴しました。大変大切なテーマですが、質問する議員も答弁者も、傍聴していた人も全て中高年ばかりで、学生の中には若い世代の声が反映されるのか危機意識をもった人もいました。
——「シルバーデモクラシー」といわれる問題ですね。それを実感することも大切な機会だと思います。それでは最後になりますが、法学部の学生やこの記事の読者へ向けて、メッセージをお願いします。
田中: 政策の現場に足を運ぶことは新しい発見の連続で、私自身も毎回ワクワクしています。是非法学部でワクワク体験を共有し、私たちがより良い公共政策を享受できるような方策を一緒に考えてみませんか。
——田中先生、本日はどうもありがとうございました。