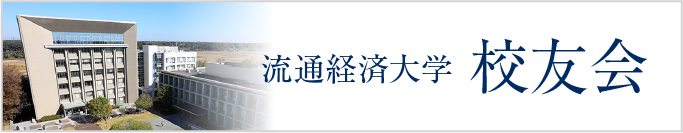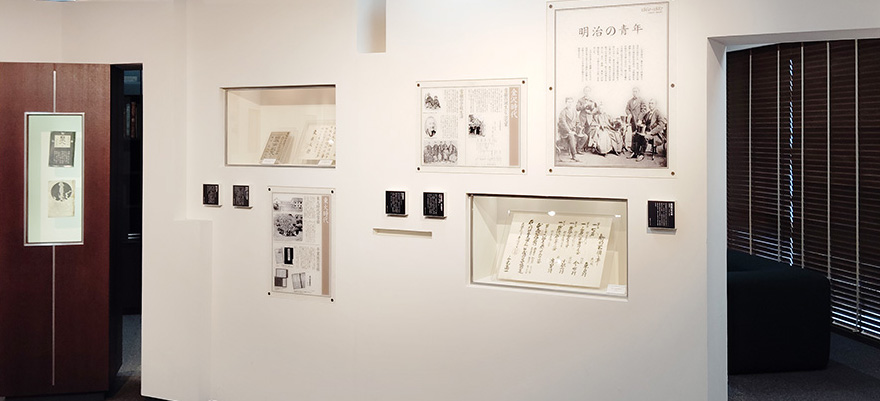【国際文化ツーリズム学科】新任教員の紹介~那須野育大先生(その2)
その1に引き続き、国際文化ツーリズム学科に4月より着任された那須野先生にインタビューしました。その2では、那須野先生の授業をご紹介いただきました。
●授業ではどのようなことを教えていますか?
現在、下部に記載の4科目を担当しています。学生の皆さんには、授業内容を単に覚えるのではなく、自分の問題意識(意見)で掘り下げて考えてもらいたいと考えています。例えば、「授業で習った○○について自分で調べてみたら、△△という事例があった」「○○について、私は△△と考える」という学生の意見を歓迎します。
【観光産業論】
本科目では、観光産業を構成する旅行・宿泊・運輸の各産業、テーマパークや文化施設、土産品・飲食サービスなど様々な産業について、そのビジネスモデルを考察します。
【ツーリズムと空間】
本科目では、日本が目指す観光立国のあり方について、観光地域づくりの観点から考察します。その際、都市と地方、日本と諸外国といったツーリズムにおける空間に着目します。
【交通ビジネス論Ⅱ】
本科目では、まず、(1)伝統的な交通論の視点から、主に交通の供給、規制政策、運賃等について解説します。次に、(2)交通論の新たな視点として、プラットフォームビジネスや経済安全保障等における交通の位置づけを考察します。
【地域マネジメント論】
本科目では、持続可能な地域経済社会の構築に向けた「地域政策」や「地域創生」のあり方について考察します。地域を取り巻く課題の解決策について、理論と事例により考察します。
●那須野先生のゼミのテーマは何ですか?
「2年演習」(2年ゼミ)のテーマは、「観光産業と地域創生」です。ゼミでは、旅行・宿泊・運輸・テーマパークなど観光産業について考察します。その際、特に、観光産業が地域創生に果たす役割を検討します。今後、観光産業では、「地域連携」が重要になると考えられます。人口減少・少子高齢化の状況下、観光産業はただ待っているだけでは、観光客を獲得できません。自ら積極的に地域と連携して、観光客を地域に呼び込む必要があります。
例えば、旅行産業では、「JTB」が会社を地域ごとに分社化しました。つまり、地域に密着して、自ら観光資源の開発を行い、観光客を呼び込んでいます。また、例えば、運輸産業では、民営化した「南紀白浜空港」が「空港発地方創生」を打ち出しました。つまり、市町村や観光地域づくり法人DMOと連携して、首都圏や外国人の観光客誘致に取り組んでいます。このような問題意識に基づき、ゼミでは、観光産業について、地域創生の観点から検討します。
ゼミでは、テーマに関する学外授業も積極的に行います。2025年4月には、インフラツーリズムの現地調査の位置づけで、防災地下神殿(首都圏外郭放水路)を見学しました(写真1)。そして同年6月には、観光文化施設の現地調査として、国立科学博物館と東京都庁を訪問しました(写真2)。この後、東京港湾地域の現地調査として、東京みなと丸に乗船予定です。

また、ゼミでは、グループごとに特定地域の観光と観光産業を調査・研究した後、研究成果をゼミ外部で発表します。外部発表の場として、他大学のゼミとの合同発表会、大学祭「つくばね祭」等を予定しています。
「3年演習」(3年ゼミ)のテーマは、「観光・交通・まちづくりに関する研究」です。現在、日本を含む先進国では、人口減少・少子高齢化に伴い、内需の減少や潜在成長力の低下、社会保障負担の増加による財政収支の悪化といった問題が懸念されています。とりわけ、日本の多くの地域は、地域産業の衰退、中心市街地の空洞化、中山間地域の過疎化といった問題に直面しています。ゼミでは、こうした地域を取り巻く課題の解決策について、「観光」「交通」「まちづくり」の観点から考察します。国内のみならず、広く国際的な視点から検討します。
ゼミでは、テーマに関する学外授業やゼミ合宿等も積極的に行います。2025年9月、福島県楢葉町の地域おこし協力隊インターンに参加して、「楢葉町のモビリティ(移動可能性)向上に関する提案」を行う予定です。この研究成果について、ゼミ外部で発表します。外部発表の場として、他大学のゼミとの合同発表会、大学祭「つくばね祭」等を予定しています。
その3に続きます。次回がラストになりますが、那須野先生のお人柄にせまりたいと思います。お楽しみに。