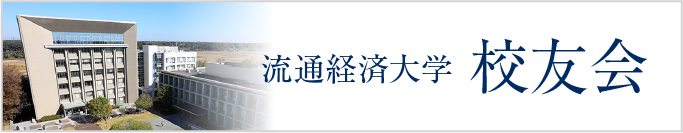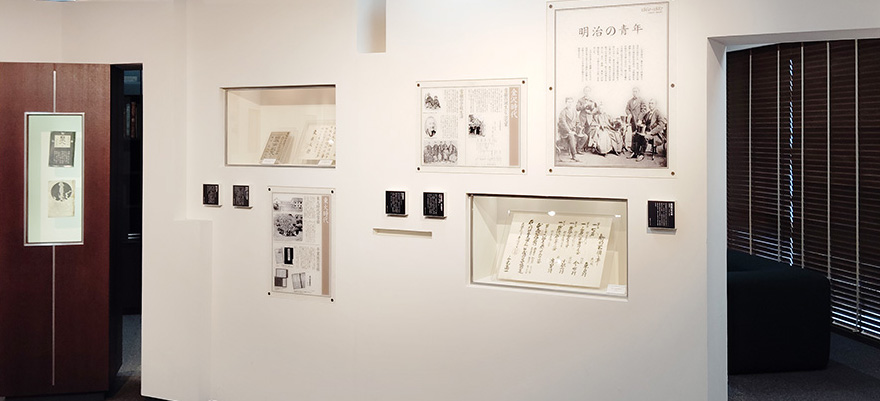【国際文化ツーリズム学科】新任教員の紹介~那須野育大先生(その1)
国際文化ツーリズム学科に4月から那須野育大准教授が着任されました。
本学科の学びの柱では「ビジネス・マーケティング」の分野の先生です。本学科の魅力ある先生の研究・授業内容や人柄を紹介すべく、那須野先生にインタビューしました。インタビューの内容は3回にわけて公開していきます。
今回はその1として、那須野先生のご専門について伺いたいと思います。 ●那須野先生の専門分野は何ですか?
●那須野先生の専門分野は何ですか?
私の専門分野は、商学・経営学に基づく「観光」と「交通」の教育・研究です。言い換えると、ビジネス・マーケティングの観点から観光産業や交通まちづくりを考えることです。
国際文化ツーリズム学科では、「観光産業論」を担当しています。観光産業を構成する旅行・宿泊・交通の各産業をはじめ、テーマパークや文化施設、土産品・飲食サービスなど様々な産業について、そのビジネスモデルを考えています。
所属学会では、観光産業のうち交通産業に着目して、「ローカル鉄道のあり方」に関する検討を行っています。近年、ローカル鉄道は、人口減少、自然災害、コロナ禍により、大変厳しい経営環境にあります。社会的に必要不可欠な一方、不採算のローカル鉄道をどのように維持存続すべきか、検討しています。
●研究者への道に進まれたきっかけはありますか?
研究者の道に進んだきっかけは、研究者であった父の影響です。とはいえ、これは1つのきっかけにすぎず、自分の進路を自分で考えて選んだつもりです。学生時代、研究者になるか、社会人になるか、かなり迷いました。その結果、世の中を広く知っておきたいと考え、社会人の道を選びました。10年間務めた後、研究者に転向した経緯があります。
●研究では何を探求されてきましたか?
研究では、観光・交通分野における「公共(政府・自治体)と民間(企業)の役割分担」について、探究してきました。「観光」と「交通」では、公共と民間の役割分担が重要です。具体的な研究テーマは、ローカル鉄道と産業観光(Industrial Tourism)の2つです。
ローカル鉄道と産業観光は、一見すると無関係のように考えられます。しかし、事業における効率性と公益性のバランスをいかに取るか、という点において、共通する部分があります。ここで「効率性」とは、主として民間(企業)の活動により、事業における無駄を省き、ヒト・モノ・カネ等の資源を有効に使うことをいいます。そして「公益性」とは、主として公共(政府・自治体)の活動により、事業における機会や成果を多くの人々に偏りなく行き渡らせることをいいます。つまり「交通」と「観光」の分野で、公共と民間がそれぞれどの程度役割を果たすか、を見極めることが重要性となります。
しかし、多くの場面において、これら効率性と公益性は相反します。状況により、いずれかを重視せざるを得ないことが多くなります。このような問題意識に基づき、観光・交通分野における「公共(政府・自治体)と民間(企業)の役割分担」について、探究しています。
●専門分野は私たちの生活とどのようなつながりがありますか?
観光産業の中の交通産業は、ヒトやモノの「移動」を司っています。よく「衣食住」と言いますが、「移動」は「衣食住」と同じかそれ以上に私たちの生活に不可欠です。
ヒトの移動については、確かに、コロナ禍を経た現在、オンライン会議や在宅勤務といった新しい働き方が普及して、仕事(通勤)での移動はコロナ前より減りました。しかし、観光など定期外の移動は、コロナ前よりむしろ増えています。この典型例は、インバウンド観光客の増加です。やはりオンライン社会となっても、リアルに交流・体験することの重要性は変わりません。
また、モノの移動についても、情報通信の発達に伴い、確かに商流(取引・決済)と情報流(情報のやり取り)はかなりオンライン化されました。しかし、物流(商品輸送)はオンライン化できず、リアルの世界で運ぶ必要があります。物流が無ければ、ネット通販のモノも届きません。
このように、ヒトとモノの移動、つまり交通産業は、引き続き、私たちの生活にとって重要な存在であり続けています。
●今はどんな研究をされていますか?
現在、「ローカル鉄道のあり方検討」に関する研究を行っています。
そもそも日本では、ローカル鉄道を含む公共交通は、「商業輸送」とされています。このため、民間企業が公共交通を収支採算前提の「商業輸送」として提供しています。しかし、欧米諸国では、公共交通が医療、福祉、教育などと同様の「公共サービス」と見なされています。このため、例えば、図書館や市民プールと同様に、公共(国や自治体)が公共交通に対して必要な資金措置や支援を行います。このことに鑑みれば、日本でも、公共交通を公共サービスとして捉え、維持存続の判断、運営の方策や資金を措置していく必要性が高いと考えられます。
このような問題意識に基づき、「ローカル鉄道のあり方検討」について研究しています。
詳しくは、リサーチマップを参照してください↓
https://researchmap.jp/nasuno-ikuhiro
その2では、授業内容について伺いたいと思います。お楽しみに。