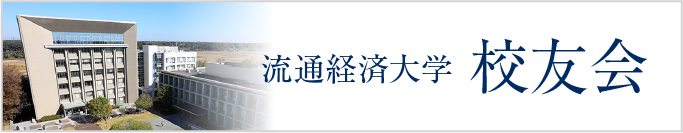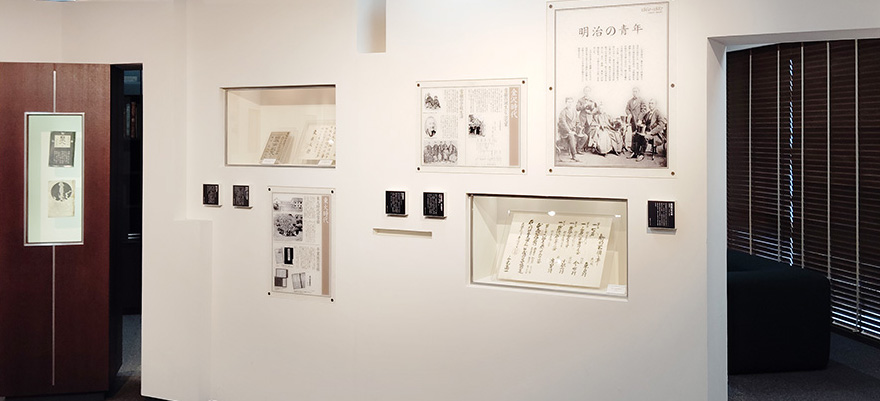法学部で広がる未来の自分の可能性 第27回 思ったよりも身近な法律?〜知られざる行政法の世界〜
「法律」と聞くと、憲法や民法、刑法などを思い浮かべる人が多いかもしれません。ですが、「行政法」もまた、私たちの生活のあらゆる場面に関わっています。それでは、そもそも行政法とはどんな法律で、どうやって勉強すれば良いのでしょうか?また、どういう点で行政法は重要なのでしょうか?これらの疑問に、法学部長でもある周先生がわかりやすく答えてくださいました。行政法の役割や学び方について、一緒に探ってみませんか?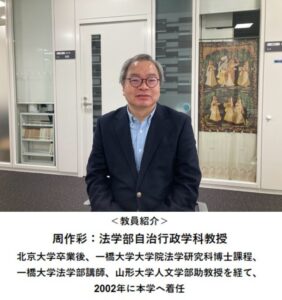
――周先生、今日はよろしくお願いします。早速ですが、行政法にあまり馴染みがない方も多いと思いますので、まずは行政法とはどのような法律なのか教えていただけますか?
周:そうですね。いわゆる憲・民・刑(憲法、民法、刑法)に比べると、行政法はあまり馴染みがないかもしれませんね。まず、そもそも憲・民・刑のように、「行政法」という名前のまとまった法律が存在しないから無理もありません。でも、身の回りのいたるところに行政法が転がっていますよ。
――「行政法」という名前の法律はないけれど、行政法はいたるところにあるというのはどういうことなのでしょうか?
周:行政法というのは、行政に関わるさまざまな法律をまとめた法分野の名前です。ですから、そこには私たちの生活にも密着したさまざまな法律が含まれているのです。
――具体的にはどのような法律が行政法に含まれるのでしょうか?
周:思いつくままにあげてみますね。たとえば、小学生でも知っている「赤は止まれ」というルールを定めている「道路交通法」、飼い犬について犬の登録や狂犬病予防注射などについて定める「狂犬病予防法」、皆さんが通ってきた小中高校・大学などについて定める「学校教育法」、家を建てるときのきまりを定める「建築基準法」、水道の供給について定める「水道法」、いざ病気などにより生活に困ってしまった人を助けるための「生活保護法」などなど。
――そういわれてみれば、たしかに私たちの生活に密接に関わる法律ばかりですね。これらがすべて行政法ということなのですか?
周:そうです。「道路交通法」はお巡りさん、「狂犬病予防法」は市役所、「学校教育法」は文部科学省や教育委員会、「水道法」や「生活保護法」も市役所など(つまり行政)が関わっています。じつは、2000本あまりある法律のうち、なんと3分の2以上、いや9割ぐらいが行政がらみの法律といわれています。
――それでは、行政法を勉強するときには2000近くの法律を学ばなければならないということですか?それはとても大変そうに思えるのですが…
周:千何百本の法律をいちいち覚えておかなければならないというなら、たしかにそれは並大抵のことではありません。でも、心配しないでください。行政法を専門としている私でも法律の名前すら正確に覚えていないものもかなりありますから。
――行政法を勉強するときには条文を覚えなくてもいいということですか?
周:条文を暗記する必要はないと思ってもらって大丈夫です。条文は「六法」と呼ばれる法令集に載っていますし、いまや法令データーベースという便利なものもありますから、スマホでも調べられますよ。
――法律の勉強というと暗記が中心になるのかと思っていましたが、そうではないのですね。では、行政法の授業の中ではどのようなことを学ぶことになるのでしょうか?
周:行政法の授業では、おもにバラバラに存在しているようにみえる無数の法律に共通するしくみやそれらのしくみを支える基本的な考え方を勉強することになります。基本的な考え方をマスターしておけば、個々の法律に使われている用語や条文の意味を理解することができるようになります。
――法律の条文を暗記するのではなく、基本的な考え方を身につけることが勉強の中心なのですね。
周:そのとおりです。この基本的な考え方とは、物理学でいう「万有引力の法則」のようなものです。「万有引力の法則」がわかれば、なぜ木の上のりんごが地上に落ちるのか、なぜ月が一定の軌道にしたがって地球の周りを回るのかを説明できるのと同じ理屈です。
――なるほど、基本的な考え方の重要性がよくわかりました。
周:ありがとうございます。たしかに「法律とりわけ行政法はむずかしい」と敬遠されることもありますが、法律の考え方をしっかり理解しておけば、経済学や社会学などに比べ法律学がむずかしいということもありませんし、あるいは憲法・民法・刑法などに比べ行政法が特別にむずかしいことも決してありません。
――ところで、行政法はいわゆる六法科目ではないと聞いたことがありますが、それは行政法はあまり重要ではないということなのでしょうか?
周:「六法」というのは、明治時代に西洋法を日本に移植するときにできた言葉でして、日本の法制度の基盤となる主要な6つの法すなわち憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の6つの法を指します。たしかに、行政法はその中に入っていません。しかし、それはその時代に行政活動が今ほど発達していなかったことの反映であって、行政法が重要でないことを意味するものではありません。行政法は、いまや憲法や民法、刑法に並ぶ重要な法分野なのです。
――そのような歴史的な背景があったのですね。ところで、いま行政法の重要さをご指摘いただきましたが、もし行政法がなかったらどうなってしまうと思いますか?
周:面白い質問ですね。じつは、行政法は2つの側面をもっています。一面では、社会の秩序(公共の利益)を守るために、行政法は、私たち市民の権利や自由を制限したりします。この意味で、もし行政法がなかったら社会は大混乱に陥るでしょう。このことは、道路交通法がなかったら現代のような車社会がどうなるかを想像してみればすぐわかるでしょう。
――道路交通法がなかったら困りますね。行政法のもう1つの側面は何ですか?
周:もう1つの側面は、国や自治体といった行政機関が好き勝手なことをしないようにコントロールするという側面です。この意味でもし行政法がなかったら、行政が好き勝手にルールを作ったり、市民の権利を無視したりする可能性が出てくるでしょう。たとえば、根拠なくあなたの土地を収用したり、税金をほしいままに徴収したりするかもしれません。行政法は法治主義の根幹におかれた、権力をしばるための歯止めでもあるのです。
――自分の身を守るためにも行政法を勉強しておいたほうがよさそうですね。
周:そのとおりです。また、行政法は、公務員になりたいと考える人にとっては必須科目です。公務員になって公平・公正な法運用をしてもらわないと、私たち市民が大迷惑をこうむるからね。
――そのとおりですね。周先生、本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。