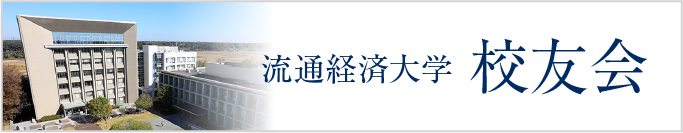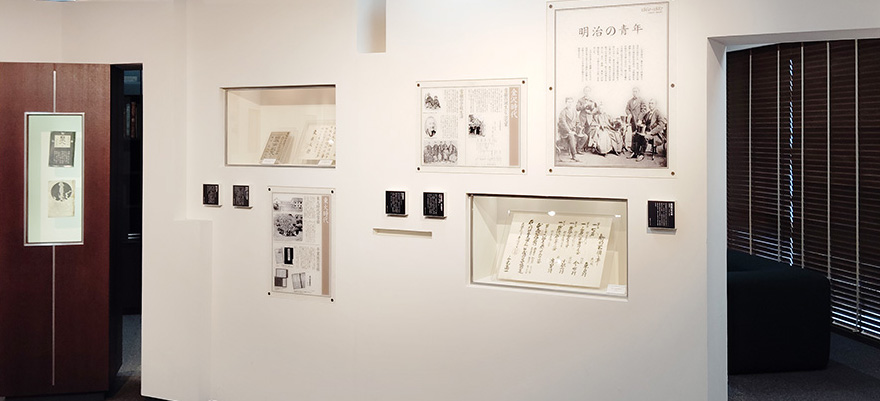ゲームで学ぶ:「公共財ゲーム」に挑戦!(経済学科:2年眞中ゼミ)
2年演習(眞中ゼミ)では、経済学における公共財についての理解を深めるために簡易的な「公共財ゲーム」に挑戦しました。このゲームでは、公共財が持つ特徴や、そこから生じる課題を体験的に学ぶことができます。
簡易的な「公共財ゲーム」の進め方は以下の通りです。
1: 各プレイヤーは自身が保有するポイント(例:10ポイント)のうち、いくつ寄付するかを決める(0~10ポイント)。
2: 全員の寄付額を合計し、それを参加者数で割った額を、全プレイヤーに均等に配分する。
この手順を複数回繰り返すなかで、プレイヤーは「自分が寄付しなくても利益を得ることができる」状況に直面します。その場合、プレイヤーはどのようにふるまうことが望ましいといえるでしょうか?これは、実際の公共財における問題を反映しているといえます。
公共財は、「非排除性:料金を支払わない人を財やサービスの消費から排除することが難しい」と「非競合性:ある人が利用していても、他の人の消費を妨げない」という性質をもつ財やサービスを指します。たとえば、公園や混雑のない一般道路、警察、消防などが該当します。公共財は誰でも利用できる一方で、料金を支払わない人、つまり費用を負担しない利用者(フリーライダー、ただ乗り)の存在によって財・サービスの適切かつ安定的な供給が脅かされるといった問題を抱えています。
「公共財ゲーム」を通じて、学生とともに、公共財を適切に供給するためにはどのような仕組みが必要なのかを議論することができました。