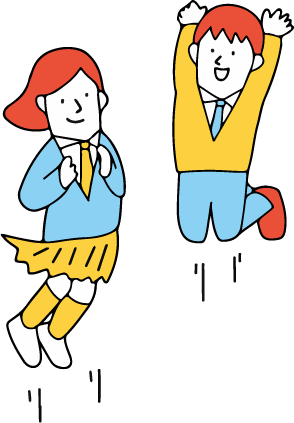法律学科
~会社法の視点から考える「食の安全」問題~

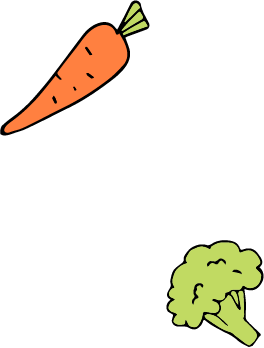
食品スキャンダルは
ステークスホルダーへの裏切り行為。
一つの不祥事が企業の大損失につながる理由
食中毒事件、期限切れ材料の使用、食材の産地や品種などの偽装、異物混入…など、近年続発している「食品スキャンダル」。しかも、日本を代表する大手企業による不祥事も多く、社会を揺るがすような事件も少なくありません。食品スキャンダルにおいて、法律面では食品衛生法や製造物責任法(PL法)、食品表示法、刑法などが関わってきますが、ここでは私の専門とする「会社法」の側面から考えていきます。
食品スキャンダルが起こると、被害を被った方はもちろんですが、企業自体も大きなダメージを受けます。スキャンダルの発覚によって企業に悪い評判が立ち、消費者離れが起こり、株価が低下し、企業価値が下がります。売上げ低下にもつながり、倒産に追い込まれるケースもあります。
一方で、投資家や従業員、取引先などのステークスホルダー(利害関係者)目線で見ると、食品スキャンダルはその企業からの裏切り行為であるとも言えます。たとえば株式会社の場合、スキャンダルによって株価が下落すると、株主は損害を被ることになるからです。
会社法では、株主を守るためのルールが定められており、企業の不祥事によって株主が損害を受けた場合、その責任を追求すべく、株主は企業に対して訴訟を起こすことができます(株主代表訴訟)。そして管理体制や教育体制などについて努力を怠ったと判断されれば、代表取締役や役員が責任を負わなければなりません。そのような事態にならないよう、企業はステークスホルダーとの良好な関係を保つための企業のあり方を考えていく必要があり、その上でも食の安全性を遵守する責任があるのです。




法学部 大学院
法学研究科 准教授
王 偉杰 先生
<専攻>
商法・会社法
- 先生が担当するゼミテーマ
- 株式会社法制
- 時事問題
- このお話に関わりのある授業
- 商法(会社法)
- 商法(総則・商行為法)
About Machine Translation
This page is translated using machine translation. Please note that the content may not be 100% accurate.
有关本网页的中文译文事宜
此网页为使用自动翻译软件译成的中文。内容不一定100%的正确,请予以理解和使用上的注意
有关本网页的中文译文事宜
此网页为使用自动翻译软件译成的中文。内容不一定100%的正确,请予以理解和使用上的注意
자동번역에 대해서
이 홈페이지는 자동번역 기능을 사용하고 있습니다. 내용이 100% 정확하지 않다는 점에 유의해 주세요.
Liên quan đến dịch thuật máy
Trang này đang sử dụng dịch vụ dịch thuật máy. Xin lưu ý rằng nội dung dịch thuật có thể không chính xác 100%.